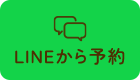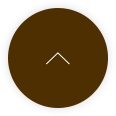潰瘍性大腸炎とは
 潰瘍性大腸炎とクローン病は炎症性腸疾患に分類されます。炎症性腸疾患とは消化管に慢性的な炎症が発生する病気で、原因がはっきりとしていません。
潰瘍性大腸炎とクローン病は炎症性腸疾患に分類されます。炎症性腸疾患とは消化管に慢性的な炎症が発生する病気で、原因がはっきりとしていません。
潰瘍性大腸炎は、大腸粘膜で慢性的な炎症が発生し、びらんや潰瘍が形成される病気です。
血便、下痢、腹痛、貧血、発熱などが代表的な症状であり、多様な合併症が起こる恐れがあります。
潰瘍性大腸炎の主な症状
初期では血便や下痢、痙攣性または持続的な腹痛が起こります。
重度の場合は、血便や下痢の頻度が多くなり、下痢による体重減少、発熱、貧血などの症状が起こります。
また、腸管外合併症として、関節や皮膚、目の症状が起こる場合があり、このような症状が治まる寛解期と再燃期(活動期)が交互に繰り返されます。
潰瘍性大腸炎の原因
現在のところ完治できる治療法がないため、厚生労働省より難病指定を受けています。遺伝的要因がある方が、食事などの環境要因によって免疫異常を起こし、発症するといわれています。
完治はできないものの、専門医の治療を受けることで、寛解期への導入・維持が可能であり、不便のない日常生活を送れるようになります。このように、適切な治療を続けることで命を落とすようなことはありません。
近年、食生活の欧米化や内視鏡検査の一般化を背景に、潰瘍性大腸炎の診断を受ける方は増えてきております。平成26年度末のデータでは17万人程度が難病登録されており、昨今は700人に1人が発症しているといわれています。また、男性は20~24歳、女性は25~29歳が最も発症しやすい年齢であり、老若男女問わず発症リスクがあります。
潰瘍性大腸炎の診断
潰瘍性大腸炎には診断基準が設けられており、様々な検査が行われます。その1つである便検査では、寄生虫や細菌が原因の腸炎ではないか調べます。また、大腸カメラ検査により大腸粘膜の組織の一部を採取して病理検査に回し、他の器質的疾患の有無を調べ、総合的に診断を下します。
潰瘍性大腸炎の分類
病変の拡大範囲から、「全大腸炎型」「直腸炎型」「左側大腸炎型」「右側または区域性大腸炎」に大別されます。発症から10年以上経っている直腸炎型以外の患者様は、大腸がんを発症しやすいといわれています。そのため、そのような方はこまめに大腸カメラ検査を受けることが大切です。
潰瘍性大腸炎の治療方法
完治できる治療法が確立されていないため、治療では大腸粘膜の炎症の抑制と症状の緩和による寛解期への導入・維持を目指します。
治療は薬物療法を行い、副腎皮質ステロイド薬や5‐アミノサリチル酸薬(5‐ASA)製剤を主に使用します。これらの治療薬の効果が不十分な場合、JAK阻害薬・抗TNFa受容体拮抗薬などを使うことを考えます。
薬物療法では炎症や症状の抑制が難しい場合や炎症と関係するがんの発症が認められる、もしくはその恐れがある場合は、大腸の全摘手術を実施します。なお、手術が必要と判断される場合は、提携先の高度医療機関を紹介いたします。
潰瘍性大腸炎の
医療費助成制度について
潰瘍性大腸炎は、公費による医療費助成を受けられる病気です。重症度分類にて病状の程度が一定以上、もしくは軽症でも一定以上の高額医療が必要となる場合は、助成の対象となります。
助成を受けるためには、受給者証が不可欠です。申請のためには、指定医療機関の難病指定医が記入した臨床個人調査票を準備し、お住まいの市区町村の保健所で手続きしていただきます。承認された場合は、申請日から受給者証が発行されるまでの期間分も遡って、助成を受けることが可能です。
クローン病とは
 クローン病は炎症性腸疾患の一種で、口から肛門までの消化管全域に慢性的な炎症が発生し、肉芽腫が形成される病気です。肉芽腫は潰瘍や線維化を伴います。
クローン病は炎症性腸疾患の一種で、口から肛門までの消化管全域に慢性的な炎症が発生し、肉芽腫が形成される病気です。肉芽腫は潰瘍や線維化を伴います。
比較的若年層が発症しやすいという特徴があり、男女比は2:1と男性の方が発症しやすく、発症数は増え続けています。発症原因は明らかになっておらず、完治できる治療法も存在しないため、厚生労働省より難病指定を受けています。
クローン病の主な症状
患者様の50%以上に下痢と腹痛の症状が起こります。症状は、病変の程度や発生部位(小腸型、大腸型、小腸・大腸型)によって違いがあります。また、狭窄や瘻孔、膿瘍などの合併症が生じ、虹彩炎や関節炎、壊疽性膿皮症、結節性紅斑、肛門部病変など、目、関節、皮膚、肛門の合併症が起こることがあります。また、クローン病は肛門周囲膿瘍を合併することが多く、肛門病変の受診をきっかけにクローン病の診断となることも少なくありません。
クローン病の原因
現時点でクローン病の明確な発症原因は不明ですが、様々な要因が複合して起こるとされています。感染症、遺伝的要因、血流の異常、食事による影響などが推測されていますが、発症に至る詳しい仕組みは分かっていません。
最新の研究では、遺伝的要因との関係が指摘されており、特に免疫細胞であるリンパ球が腸内細菌や食事に過度に反応することで発症に至るのではと推測されています。
クローン病の診断基準
画像検査や内視鏡検査、病理検査によってクローン病特有の所見が発見された場合、クローン病の診断基準に則り、包括的な診断を下します。
また、クローン病は肛門疾患を合併することが多く、肛門病変をきっかけにクローン病の診断に繋がることがあります。
クローン病の治療方法
クローン病の治療法としては、薬物療法や栄養療法などの内科治療と外科治療があります。クローン病を完治できる治療法は存在せず、治療は患者様の日常生活の負担を減らすことを目標に行います。
内科治療が中心となり、穿孔や腸閉塞、膿瘍などの合併症に対しては外科治療を実施します。昨今は抗TNFa受容体拮抗薬が使用されるようになったため、手術をするケースは少なくなってきています。
重度の炎症や症状がある場合、副腎皮質ステロイドや5‐アミノサリチル酸製剤、免疫調整薬などを使用します。免疫調整薬や5‐アミノサリチル酸製剤の使用によって症状が軽減されても、自己判断により治療を中断すると再燃期に移行する恐れがあるため、医師の指示に従って治療を続けましょう。治療効果が乏しい場合、抗TNFa受容体拮抗薬などを使うことがあります。
栄養療法
クローン病は食事による刺激から症状が悪化することがあり、消化管を安静にするために食事管理が必要です。病状が安定している場合は、いつも通りの食事が可能ですが、食事による症状の悪化を防ぐために、基本的には低残渣で低脂肪の食事を推奨しています。
なお、栄養補給が不十分な場合は経腸栄養剤を服用します。経腸栄養剤には、アミノ酸を主体とした「無脂肪成分栄養剤」、少量のタンパク質と脂肪を含む「消化態栄養剤」があります。
また、小腸で重度の病変や狭窄が生じている場合、点滴から栄養素を投与する完全静脈栄養法を実施します。
外科治療
狭窄、穿孔、膿瘍などの合併症が起こっている場合、外科治療が選択されます。穿孔・膿瘍に対しては外科治療を実施し、重度の狭窄に対しては内視鏡的拡張術を実施します。腸管をできるだけ残すために、切除範囲は最小限に留めます。
注意事項
クローン病は潰瘍性大腸炎とは異なり、腸管壁の深層まで炎症が広がります。また、炎症が頻発することで腸管へのダメージが蓄積し、狭窄などの合併症が起こりやすいといわれています。そのため、症状が安定する寛解期への早期導入・維持が大切です。
なお、体調が良いと感じる時でも病状が悪化している場合があるため、定期的な経過観察が欠かせません。
また、日常生活では、動物性脂肪の摂取を避ける食事療法を継続することが大切です。