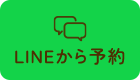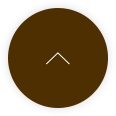健康的な便の色
基本的に、健康的な便は茶色です。消化・吸収が適切に行われると、便に胆汁の色素や食べ物の代謝産物が混ざり、茶色になります。なお、服用した薬や食べ物、病気などの影響を受けるため、便の色は人によって若干の違いがあります。
血便の色
血便は、基本的に鮮やかな赤もしくは黒っぽい色です。なお、出血部位や血液の量によって違いが出ます。
鮮やかな赤色の血便は、肛門周辺や直腸の出血によって起こることがほとんどです。この場合、比較的肛門に近い場所で出血していることを示します。
一方、黒っぽい血便は、胃などの上部消化管や小腸からの出血によって起こることがほとんどです。消化液によって血液が酸化し、黒っぽい便になります。このような血便は「メレナ」といわれる場合もあります。
黒色便は大腸がん?
大腸がんに特徴的な便の色はなく、便の色から大腸がんを診断することは困難です。基本的に、大腸がんによって便の色が変わる場合は様々な色が考えられ、色が変わる原因は多岐にわたります。
なお、大腸がんが悪化して腫瘍が巨大化すると、便が通過する際に擦れて出血し、便に血液が混入して黒っぽい便になることがあります。黒っぽい便はメレナといわれ、消化管の出血が起こっている恐れがあります。しかし、黒っぽい便でも大腸がん以外の病気や薬の副作用が原因となっている場合もあります。
便の色から分かる病気
| 便の色 | 原因 |
|---|---|
| 緑色の便 | 胆汁の排泄と関係しており、胆汁に含まれるビリルビンの増加、消化管の運動異常、食べ物による影響などによって緑色の便になることがあります。基本的には食べ物による軽微な影響であり、自然に元の色に戻ります。 |
| 黄色の便 | 健康的な便は黄褐色~茶褐色となっており、これは消化酵素や胆汁に含まれる色素が影響しています。なお、黄色の便となっている場合は、胆道の異常や脂肪吸収障害の可能性があります。 |
| 灰色または 白色の便 |
胆汁の排泄異常の恐れがあり、肝臓や膵臓の病気、胆道の病気、胆のうの異常などによって排泄されることがあります。 |
| 黒色の便 (メレナ) |
消化管出血の恐れがあります。食道や胃などの上部消化管の出血、胃・十二指腸潰瘍、大腸の出血などによって排泄されることがあります。 |
| 白色の便 |
胆汁の排泄異常の恐れがあり、胆道や肝臓の病気、胆のう炎、胆石などによって排泄されることがあります。 |
便の色に影響を与える食品
| 便の色 | 食品 |
|---|---|
| 緑色の便 | 葉物野菜や緑野菜に含まれる塩基性成分や葉緑素の影響で、緑色の便になる場合があります。 |
| 赤色の便 | クランベリー、赤大根(ビーツ)、人参などの赤い食べ物を食べると、これらの食べ物の色素が便に移り、赤色の便になる場合があります。 |
| オレンジ色の便 | 人参やカボチャなどカロテノイドやビタミンが豊富に入っている食品を食べると、オレンジ色の便になる場合があります。 |
| 黄色の便 | 脂肪や油分の過剰摂取によって、黄色の便になる場合があります。また、食品添加物やビタミン剤の黄色の着色料が原因となる場合もあります。 |
| 白色の便 | 胆道の異常や脂肪吸収不良によって、白色の便になる場合があります。また、乳製品の過剰摂取が原因となる場合もあります。 |
便の色に影響を与える薬
| 薬 | 便の色 |
|---|---|
| 鉄剤 | 貧血の治療に使われる鉄剤によって、消化管の中で鉄の酸化反応が起こり、黒っぽい便になる場合があります。 |
| ビタミンB群 | ビタミンB群の一部を摂り過ぎると、明るい黄色の便になる場合があります。特に、ビタミンB2(リボフラビン)の過剰摂取が原因となるといわれています。 |
| 抗生物質 | 抗生物質によって腸内細菌のバランスが変化するため、便の色が変わる場合があります。一部の抗生物質の使用によって、水っぽい便や緑色の便になる場合があります。 |
| ビスマス製剤 | 胃腸炎や消化性潰瘍の治療で使われるビスマス製剤によって、黒っぽい便になる場合があります。 |
便と一緒に黄色い油が出る
とき考えられること
 乳白色~薄黄色の便と一緒に油が出て浮いている場合、脂肪便が疑われます。脂肪便が時々出るくらいでしたら大きな問題はありませんが、1週間以上続いている場合は慢性膵炎の可能性があるため、なるべく早めにご相談ください。
乳白色~薄黄色の便と一緒に油が出て浮いている場合、脂肪便が疑われます。脂肪便が時々出るくらいでしたら大きな問題はありませんが、1週間以上続いている場合は慢性膵炎の可能性があるため、なるべく早めにご相談ください。
慢性膵炎は膵臓で慢性的な炎症が生じている状態であり、脂肪便の他にもみぞおちや背中の痛み、食欲不振などの症状が起こる場合があります。膵臓には消化酵素を分泌する働きがありますが、慢性膵炎によって消化酵素の分泌が減少し、糖尿病や消化不良が発生する恐れもあります。
また、膵臓がんによって脂肪便が出る場合もあります。膵臓がんは早期発見しづらいため、症状が起こった段階での早期受診が大切です。膵臓がんは悪化すると治療が困難となるため、早期発見・早期治療に努めましょう。