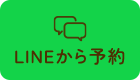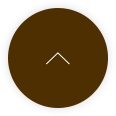逆流性食道炎とは
 逆流性食道炎とは、胃酸など胃の内容物が逆流して食道粘膜に炎症が発生する病気です。通常、食道粘膜は胃酸に晒されることはないため、胃とは異なり粘膜を保護する機能がなく、胃酸が逆流すると食道粘膜に炎症が発生します。逆流は下部食道括約筋という筋肉により防がれていますが、加齢によってこの筋肉が緩まると逆流性食道炎のリスクが上がります。また、肥満や腹部を圧迫する服装による腹圧の上昇、過剰なタンパク質や脂肪など消化に時間がかかり胃酸の分泌が増加する食事も原因となるため、様々な年代で発症者数が増え続けています。
逆流性食道炎とは、胃酸など胃の内容物が逆流して食道粘膜に炎症が発生する病気です。通常、食道粘膜は胃酸に晒されることはないため、胃とは異なり粘膜を保護する機能がなく、胃酸が逆流すると食道粘膜に炎症が発生します。逆流は下部食道括約筋という筋肉により防がれていますが、加齢によってこの筋肉が緩まると逆流性食道炎のリスクが上がります。また、肥満や腹部を圧迫する服装による腹圧の上昇、過剰なタンパク質や脂肪など消化に時間がかかり胃酸の分泌が増加する食事も原因となるため、様々な年代で発症者数が増え続けています。
胸焼けなどは市販薬でも改善することがよくありますが、何度も逆流が起こると慢性化していきます。食道粘膜の炎症が慢性化するとがんを発症しやすくなるため、逆流性食道炎の症状が慢性化している場合は消化器内科を受診して治療を受け、再発防止に努めましょう。
逆流性食道炎の主な症状
- 胸焼け
- みぞおちや胸の痛み
- 胃もたれ
- 呑酸(胃酸が口元まで上がってくる感じ)
- のどの違和感
- 飲み込みにくさ
- つかえ
- 長引く咳
- 声がれ
など
逆流が起こる原因・病気
食道裂孔
胸部と腹部は横隔膜によって隔てられており、食道は横隔膜の食道裂孔を通って腹部に到達します。加齢などが原因で食道裂孔による締め付けが緩んでしまった場合、逆流リスクが高まります。また、食道裂孔が弛緩すると胃の上部が胸部に飛び出す食道裂孔ヘルニアが発生する場合があり、逆流リスクが高まります。
下部食道括約筋(LES)
胃酸の逆流は、胃と食道の繋ぎ目にある下部食道括約筋の働きによって防がれています。しかし、加齢などが原因で筋肉が弛緩すると、逆流リスクが高まります。
蠕動運動
消化管は蠕動運動を行うことで内容物を先の臓器に送ります。逆流が発生しても蠕動運動が盛んに行われていればすぐに胃に戻されますが、蠕動運動の働きが衰えると、逆流したものが食道に長期間滞留して炎症が発生しやすくなります。
腹圧
腹圧が上昇すると胃の圧力が増して逆流リスクが高まります。腹圧が上がる原因としては、衣類による締め付け、肥満、運動、猫背などの姿勢の乱れ、重いものを持ち上げるなどが考えられます。
生活習慣
食後すぐに寝ると逆流リスクが高まります。また、消化しづらいタンパク質や脂肪を過剰摂取するなど、食習慣が乱れることで胃酸が過剰に分泌されるようになます。そして、逆流性食道炎を発症しやすくなります。
内服薬
病気に使用される治療薬の副作用によって下部食道括約筋が弛緩し、逆流性食道炎を発症することも少なくありません。原因となる治療薬は、心疾患・喘息・高血圧の薬など様々あるため、日頃から飲んでいる薬があれば、受診の際に薬を確認するために薬手帳などを持参ください。副作用が原因で逆流が発生している場合、処方内容を切り替えることで逆流を防げることもあります。処方内容の変更が難しい場合も、炎症が繰り返し起こらないように、治療を続けて症状を解消することが大切です。
なお、ピロリ菌の除菌治療後、胃酸の分泌が回復する過程で一時的に逆流性食道炎の症状が発生することがあります。この場合は特段の治療は不要ですが、激しい症状が起こっている場合は薬により症状を解消できますので、一度ご相談ください。
逆流性食道炎の検査
胃カメラ検査では食道粘膜をリアルタイムで確認し、疑わしい組織を採取して病理検査に回すことで、確定診断に繋げられます。逆流性食道炎や食道裂孔ヘルニアと同様の症状を示す病気は様々ありますが、これら病気が起こっていないかチェックすることも可能です。また、炎症の状態や範囲を詳しくチェックすることで、有効な治療を行えるようになります。
レントゲン検査とは異なり、胃カメラ検査は被ばくのリスクがなく安心安全な検査です。当院では、経験豊富な消化器内視鏡専門医が最新の内視鏡システムを駆使し、細心の注意を払って胃カメラ検査を実施します。また、鎮静剤を使って半分眠ったような状態で検査を受けることも可能ですので、胃カメラ検査に抵抗感がある方も一度ご相談ください。
逆流性食道炎の治療
逆流性食道炎の治療では、胃酸分泌を抑制する薬などにより逆流症状や炎症を抑え、生活習慣の見直しにより再発を防ぎます。症状が改善しても炎症が完治しないと何度も再発するため、専門医による適切な治療を受けましょう。
薬物療法
治療では、胃酸分泌を抑えるプロトンポンプ阻害薬(PPI)やH2ブロッカーを主に使用し、各患者様の症状に応じて蠕動運動などの働きを向上させる消化管運動機能改善剤、粘膜保護剤、胃酸を中和する制酸剤なども使用します。症状そのものは薬を飲み始めると比較的早期に改善しますが、炎症はまだ続いているため、症状が治まったからといって患者様の判断で内服を止めてしまうと、再発する可能性が高いです。逆流性食道炎の再発・食道がんの発症リスクを抑えるためにも、医師の指示に従って内服を続けるとともに、生活習慣の見直しも並行して行いましょう
服薬について
薬のほとんどは、効果が最大化するように食前・食後・食間など内服する時間が決まっています。そのため、医師の指示に従って内服していただくことが大切です。内服によって薬を消化管に直接送ることが可能であり、薬は分泌される消化液などの成分に応じて作られているため、指示を守って服用していただくことで満足な効果が見込めます。
また、粘膜の状態を正常化し、再発を防止するためには、症状が治まってからも一定期間は服用を継続しなければなりません。何度も再発することで食道がんの発症を招くのを防ぐためにも、医師の指示に従って服用してください。
当院では、なるべく患者様のご希望に合わせて薬をお渡ししています。薬についてお悩みがあれば、どんなことでも遠慮なくご相談ください。
生活習慣の改善
逆流性食道炎の発症・重症化の原因となる腹圧の上昇や胃酸の分泌を促す食事など、生活習慣を見直すことは再発を防ぐために必要です。長期的に継続することが大切ですので、無理なくスタートできるものから取り組んでみましょう。
食生活
タンパク質や脂肪の過剰摂取は消化に時間がかかり、胃酸の分泌も増加するため、逆流のリスクが上がります。また、甘いものや香辛料などの刺激物も逆流のリスクが上がるため、過剰摂取は禁物です。さらに、喫煙や飲酒もリスク要因となるため、なるべく禁煙・節酒できるようにしましょう。
その他、便秘は腹圧が上がるため、食物繊維や水分を意識して摂取し、改善や予防に努めましょう。当院では、便秘が長引いている方に対して、便秘改善も含めた総合的な治療を実施します。
腹圧
胃が圧迫されることで逆流しやすくなるため、大きな腹圧がかからないようにしてください。腹圧が上がる原因としては、衣類やベルト、肥満、運動、猫背などの姿勢の乱れ、重いものを持ち上げる動作などが挙げられます。そのため、原因に応じた生活習慣の見直しを行うことが重要です。当院では、原因を確認して患者様としっかり相談した上で、具体的な見直し方法をご案内します。
その他
食後すぐに寝ると逆流が発生しやすいため、食後2時間以上経ってから寝るようにしてください。また、寝ると咳が出る方は、逆流によってのどに刺激が加わっている可能性があります。クッションなどを使って上半身を高くして寝ると咳の症状が軽くなることがありますので、試してみてください。