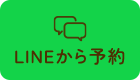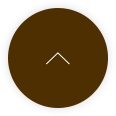過敏性腸症候群(IBS)とは
 過敏性腸症候群とは、炎症、潰瘍、がんなどの器質的異常が検査で発見されないにもかかわらず、便秘や下痢、腹痛、膨満感などが長引く病気です。
過敏性腸症候群とは、炎症、潰瘍、がんなどの器質的異常が検査で発見されないにもかかわらず、便秘や下痢、腹痛、膨満感などが長引く病気です。
急激な下痢が起こるなど、日常生活に多大な悪影響が及びます。昨今、発症数が増え続けている病気ですが、機能改善によって症状解消が期待できます。
過敏性腸症候群の主な症状
下痢型・便秘型・交代型に大別され、その他にも腹部膨満感などが生じるガス型という種類もあります。
便通異常のほか、腹部の違和感や腹痛などの症状が起こります。腹痛は、急激な腹痛が起こる場合と鈍い腹痛が長引く場合に分けられます。腹痛が生じた際は便意も催すことがありますが、ほとんどは排便すると一時的に腹痛が改善します。
消化器以外の症状としては、疲労感や頭痛、抑うつ症状、不安感、集中力の低下などが起こります。強い緊張によるストレスや食生活の乱れによって起こるため、就寝中に症状が起こることは稀です。ガス型では腹部膨満感のほか、おならの頻発や腹鳴などの症状が起こります。
下痢型
急激な便意と腹痛によって、重度の下痢症状が起こります。
急激に症状が起こるため、通学・通勤などで利用する電車やバスなどで近くにトイレがない環境が心配になってしまいます。そして、このストレスから症状が重くなるという負の連鎖に陥り、外出が困難になります。
便秘型
激しい便秘と腹痛が起こりますが、強くいきんでも排便が難しくなります。排便できても、ウサギの糞のような小さくてコロコロした便が少し出る程度です。腸管の痙攣が原因で便が腸内に留まることによって起こります。
交代型
下痢・便秘の症状が交互に発生します。また、激しい腹痛も起こります。
過敏性腸症候群の症状の原因
消化管の機能は自律神経によって制御されているため、ストレスなどの精神的負担によって自律神経が乱れることで、消化管機能が低下してしまいます。
消化管の知覚過敏や機能低下などによって症状が起こることがほとんどですが、その他にも精神的ストレスによって症状が現れます。また、感染性腸炎をきっかけに過敏性腸症候群を発症することから、免疫異常との関係性もあると考えられています。
過敏性腸症候群の診断
別の消化器疾患でも同様の症状が起こるため、最初に器質的異常が起こっていないかを確認します。別の消化器疾患でないことが分かったら、世界的な診断基準であるRome基準に則って診断します。以前まではRomeIII基準が用いられていましたが、現在は2016年に制定されたRomeIV(R4)基準が採用されています。血液検査の結果や病変からは診断が不可能なため、患者様のお悩みの症状を確認しつつ基準を参考に診断を下します。
また、器質的疾患が起こっているか確認するために、大腸カメラ検査・便検査・尿検査・血液検査を実施します。
RomeIV(R4)
症状が6ヶ月以上前から続いており、腹部の違和感や腹痛が直近3ヶ月間に最低でも週1日以上起こっていて、以下の項目の2つ以上に当てはまっていると、過敏性腸症候群の診断となります。
- 排便によって腹痛などの症状が改善する
- 症状があるか無いかによって、便の状態が変わる
- 症状があるか無いかによって、排便頻度が変わる
過敏性腸症候群の治療方法
過敏性腸症候群は、急激な便意などによって日常生活に悪影響を及ぼします。
命を落とすような病気ではありませんが、完治できる治療法が存在せず、根気強く治療を継続することが重要です。
当院では、患者様のお悩みをなるべく軽減し、症状を解消できるよう治療を実施します。具体的には、睡眠や食事などの生活習慣の見直しと薬物療法を行います。
生活習慣の改善
偏った食生活や睡眠不足などの生活習慣の乱れ、ストレスや疲労など、過敏性腸症候群の症状を悪化させる原因を取り除きます。
喫煙やお酒の飲み過ぎ、刺激物の摂り過ぎなども控えていただきます。ストレスが関係するため、無理のない範囲で焦らず着実に取り組んでいくことが重要です。
運動療法
早歩きの散歩やウォーキング、ストレッチ、ジョギング、水泳などを習慣化して、血流を向上させることで、腸の機能を正常に近づけます。
薬物療法
日常生活に影響を及ぼすような急激な腹痛や便意などの症状が起こっている場合、薬物療法を実施します。
便秘や下痢に効果がある薬を使って症状を改善させます。薬の種類は様々あるため、患者様の症状に応じた適切な薬を処方します。重度の症状がある場合、短期的に抗うつ薬や抗不安薬を処方する場合があります。その他、新薬や漢方薬、乳酸菌製剤なども処方しています。
過敏性腸症候群が疑われるような症状がある場合、お気軽に当院までご相談ください。