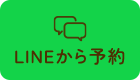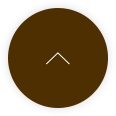- おならの臭いは何の臭い?
- おならの臭いが臭い!何が原因?
- おならが臭いと大腸がんの疑いがある?
- おならは1日何回くらいが正常?
- おならの音の大きさが気になる方へ
- おならの臭い・回数を改善するために
心がけること
おならの臭いは何の臭い?
 おならの臭いは、腸内細菌が食べ物を分解する際に出るガスに起因します。食べ物の成分によってガスのタイプに違いがあるため、おならの臭いは食べ物と関係しているとされています。例えば、食物繊維を分解する際に出るガスは、ほぼ臭いがないメタンガスや水素ガスです。一方で、ネギや肉、にんにくなどイオウ成分が豊富な食べ物を食べると、これらが分解・腐敗する過程で出る強い悪臭があるスカトールやインドールが生じます(糞便のような悪臭がする場合があります)。おならの99%は水素、窒素、酸素、二酸化炭素、メタンなどの臭いがないガスでできており、残りの1%は酪酸、硫化水素、スカトール、インドール、アンモニアなどの悪臭を放つガスでできています。
おならの臭いは、腸内細菌が食べ物を分解する際に出るガスに起因します。食べ物の成分によってガスのタイプに違いがあるため、おならの臭いは食べ物と関係しているとされています。例えば、食物繊維を分解する際に出るガスは、ほぼ臭いがないメタンガスや水素ガスです。一方で、ネギや肉、にんにくなどイオウ成分が豊富な食べ物を食べると、これらが分解・腐敗する過程で出る強い悪臭があるスカトールやインドールが生じます(糞便のような悪臭がする場合があります)。おならの99%は水素、窒素、酸素、二酸化炭素、メタンなどの臭いがないガスでできており、残りの1%は酪酸、硫化水素、スカトール、インドール、アンモニアなどの悪臭を放つガスでできています。
おならの臭いが臭い!何が原因?
食生活が原因でおならの臭いが臭くなる場合があります。例えば、肉類の過剰摂取によって腸内の悪玉菌が増加し、臭いの元となる場合があります。また、玉ねぎやにんにくなどイオウ成分が豊富な食べ物を食べると、スカトールやインドールなどの臭い成分が生じる場合があります。さらに、牛乳を飲むとお腹を壊しやすい方(乳糖不耐症)は、乳製品を摂取するとおならが出やすくなるため、摂り過ぎないようにしてください。コーヒーを飲み過ぎると消化しづらくなる場合があり、臭いの元となることもあります。お酒を分解する際に出るアセトアルデヒドも悪臭の原因となるため、飲酒は程々にしましょう。
バランスの整った食生活を意識し、摂り過ぎないようにすることで、おならの臭いを改善できる場合があります。
おならが臭いと
大腸がんの疑いがある?
大腸がんは進行すると便の通過に障害をきたし、便秘や下痢が起こることがあります。便が腸内に長期間留まることで、腸内細菌によるガスの生成が増加する場合があります。また、がん細胞の代謝産物や腸内細菌叢の変化によりおならの臭いが強まります。
おならの臭いや排便状況で不安がある方は、一度当院までご相談ください。
おならは1日何回くらいが正常?
おならの回数は人によって異なりますが、基本的に1日に10回くらいが正常の範囲内といわれています。なお、1日に数回から数十回までバラツキがある場合もあり、患者様の食生活や健康状態、腸内環境によって差が出ることがあります。
また、おならの回数のみで健康状態を判定することは困難なため、おならの臭いが強かったり、不快感や膨満感も起こっていたりする場合は、消化に異常がないか調べることをお勧めします。
おならの音の大きさが
気になる方へ
おならの音の大きさは、
以下のような要因によって変わります。
ガスの量
おならの音の大きさは、ガスが出る量によって変わります。ガスが多いほど音は大きくなります。
腸の動き
腸の働きが活発な時にガスが一気に出ると、音が大きくなる場合があります。
括約筋の状態
ガスが出る際に内臓の括約筋(特に肛門周辺の括約筋)がどの程度開くか、もしくは閉じられているかによって音の大きさが左右される場合があります。
肛門の形状
肛門の形状によって、ガスが出る際の音の響きが左右される場合があります。
腸内の状態
腸内環境の変化や腸内細菌の活動によって、おならの音が左右される場合があります。
おならの臭い・回数を改善するために心がけること
食事のスピード
食事はよく噛んでゆっくり食べましょう。よく噛むと唾液の分泌が増加し、大量に空気を吸い込みづらくなります。よく噛まずに早食いすると、大量に空気を吸い込み、ガスの量が増える場合があります。また、よく噛まないと消化に時間がかかり、食べ物が腸内に滞留しやすくなって、腐敗する場合もあります。これにより、おならの臭いが強くなるため、食べ物はよく噛んでゆっくり食べるようにしましょう。
食べ物
おならの臭いが強い場合、食事内容を改善しましょう。腸内の悪玉菌によって臭いが強くなります。乳酸菌を意識して摂り、食事の栄養バランスに注意しましょう。ヨーグルトには多様な菌が入っており、どの菌が合うかは個人差があります。腸内細菌叢のバランスは個人差があるため、ご自身に合う菌を含むヨーグルトを選ぶことが大切です。そのためには、特定の食品を2週間食べてみて、便秘などが解消されるかをチェックしてみましょう。
食物繊維
食物繊維を意識して摂取しましょう。食物繊維を豊富に摂ることで、腸内環境が整い、軟便や便秘などの腹部の異常の改善が見込めます。軟便や便秘によっておならが出る場合は、食物繊維を豊富に摂り、腸内環境を改善することが大切です。
水溶性食物繊維は、腸内の善玉菌のエサとなって、善玉菌を増やします。一方で、不溶性食物繊維は便の量を増やして腸に刺激を与えることで、排便を促進します。食物繊維が多く含まれる食品としては、ごぼう、トマト、押し麦、小麦、豆類、いも類、果物などが挙げられます。なお、不溶性食物繊維を摂り過ぎると、便秘が重症化することもあるため、適度なバランスを維持することが大切です。
便秘
便秘を改善し、腸内環境を正常に近づけることも重要です。食べ物が腸内で長期間滞留すると、過剰なガスが出ておならが増えます。
便秘が長引いている場合は、腸内環境を改善するために一度専門医に相談することをお勧めします。