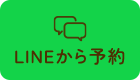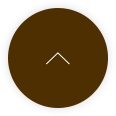食道静脈瘤とは
 食道の静脈が拡張してくねくねと曲がり、瘤のように膨らんでいて、目視で確認することが可能な状態を、食道静脈瘤といいます。
食道の静脈が拡張してくねくねと曲がり、瘤のように膨らんでいて、目視で確認することが可能な状態を、食道静脈瘤といいます。
肝硬変の患者様の7割程度が併発するといわれており、静脈瘤が進行すると破れて消化管出血が発生する恐れがあります。
現代医療のレベルは上がっておりますが、静脈瘤が破れると2割程度の方が命を落とす危険性があります。そのため、破れるリスクがある場合は予防治療を受けることが欠かせません。
食道静脈瘤の症状
静脈瘤そのものは無症状ですが、
静脈瘤を引き起こす肝硬変などの
基礎疾患が原因となる症状が起こります。
肝硬変の主な症状(食道静脈瘤が破裂した場合の症状)
全身倦怠感や疲労感、食欲不振などの症状をきたします。悪化すると、白目や皮膚が黄色くなる黄疸、むくみ、腹水などの症状も起こる場合があります。静脈瘤が生じると、ちょっとした刺激で損傷して出血が起こりやすくなります。大量出血すると命を落とすリスクもあり、肝硬変の3大死亡原因の1つとされていますので、注意が必要です。食道静脈瘤が破れると、次のような症状が起こります。
- 貧血
- 下血(真っ黒なタール便)
- 吐血(黄色っぽい胃液と鮮血が混ざったもの)
食道静脈瘤の原因
肝硬変などの肝臓の異常によって起こる門脈圧の上昇(=門脈圧亢進)が食道静脈瘤の代表的な原因です。
また、肝硬変の他にも、バッド・キアリ症候群、慢性膵炎、特発性門脈圧亢進症、膵がん、肝がんなどによって門脈圧が上昇します。
食道静脈瘤の検査・診断
胃カメラ検査やバリウム検査、経皮経肝門脈造影検査(PTP)、CT検査などで検査・診断します。
なお、バリウム検査、経皮経肝門脈造影検査(PTP)、CT検査などは当院で対応していないため、必要な場合は提携先の医療機関を紹介いたします。
食道静脈瘤の治療
出血の治療を行うことが必要です。
具体的には、次の2つの内視鏡を用いた
治療法が基本となります。
食道静脈瘤硬化療法(Endoscopic injection sclerotherapy: EIS)
食道静脈瘤の内視鏡的治療法として一般的に実施されている治療法です。
内視鏡を使って静脈瘤を観察しながら、注射針により硬化剤を流し込み、静脈瘤を硬化させます。
なお、当院では行っておりませんので、この治療を行う場合は提携先の医療機関をご紹介いたします
内視鏡的静脈瘤結紮(けっさつ)術
(Endoscopic variceal ligation: EVL)
食道静脈瘤を内視鏡で縛って除去する治療法です。
EISよりも患者様に負担がかかりづらく、簡単に行えてリスクも小さいといわれていますが、再発しやすいというデメリットもあります。
昨今は、EVLとEISそれぞれのメリットをうまく活用して一緒に行う事例も多くなっています。
なお、当院では行っておりませんので、この治療を行う場合は提携先の医療機関を紹介いたします。
食道静脈瘤を早期発見、
早期治療するために
体の外の診察や血液検査では食道静脈瘤ができているか確認することはできません。
静脈瘤そのものは無症状のため、発症を自覚できずに静脈瘤が悪化し、破れて大量出血が生じる恐れもあります。大量出血によって体内の血液が足りなくなってショック状態に陥ると、命を落とす危険性もあります。
破れた静脈瘤は内視鏡を使って効果的に治療できますが、出血が治まっても全身の血液量が一時的に足りなくなることで、様々な臓器に悪影響が及ぶ恐れがあります。したがって、静脈瘤が破れないように予防治療を行うことが大切です。
静脈瘤の状態を確認するためには、内視鏡検査を定期的に受けて経過を観察することが欠かせません。破れる可能性が高い静脈瘤(ハイリスク静脈瘤)は内視鏡で観察することが可能です。ハイリスク静脈瘤には、ミミズのようにくねくねと血管が広がっている、赤く腫れ上がって血豆のように見える、血管が数珠のように膨張してくねくね曲がっているなどの所見を確認できます。これらの所見があれば、予防治療を行うことが不可欠です。特に、肝硬変を患っている方は、胃カメラ検査を定期的に受けることをお勧めします。