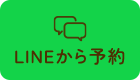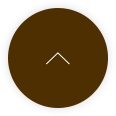血便が出たらどうしたらいい?
 血便と一言でいっても形態は様々あり、便に血が混入しているものや便全体が黒くなっているものなどがあります。また、目視できないほど微量の血液が混ざっていることもあり、便潜血検査をきっかけに血便が見つかることもあります。
血便と一言でいっても形態は様々あり、便に血が混入しているものや便全体が黒くなっているものなどがあります。また、目視できないほど微量の血液が混ざっていることもあり、便潜血検査をきっかけに血便が見つかることもあります。
血便は、消化管のどこかで出血していることを示します。大腸がんなどの深刻な病気によって血便が出ることもあり、血便が出たら消化器内科に相談し、出血部位を特定して治療を受けることが大切です。受診の際に便の状態を詳しく教えていただけると、適切な検査をスムーズに行えます。
血便と下血は同じ?違う?
原因の病気は?
血便と下血は医学的には別の病態とされています。下血は、肛門から排出される血液成分の総称で、食道・胃・十二指腸・小腸・大腸などの消化管全体のどこかで出血していることを示します。血液が混ざった便、血液のみ出る場合も下血に含まれます。対して、血便は下血の一種で、下部消化管(大腸)からの出血により血液が混ざった便が出る状態です。
下血
食道・胃・十二指腸・小腸・大腸などの消化管全体のどこかで出血していることを示します。
血便
下血の中で特に下部消化管(大腸)から出血していることを示します。
主な血便の病気
(肛門の病気?大腸の病気?)
大腸や肛門の病気の症状として
血便が出る場合があります。
代表的な病気としては次のようなものがあります。
肛門の病気
いぼ痔
内痔核と外痔核に分類され、妊娠・出産、排便時の強いいきみなどによって起こります。
切れ痔
下痢や便秘が慢性化することが原因となり、皮膚が裂けて出血し、便に混ざることで血便が出ることがあります。
肛門ポリープ
切れ痔が何度も再発することでできたポリープです。ポリープが切れることで、血便が出ることがあります。
大腸の病気
大腸ポリープ・大腸がん・直腸がん
便の通過時に接触して出血が生じ、鮮やかな赤色の血液が大量に出る傾向にあります。
直腸粘膜脱
排便時のいきみによって直腸粘膜が脱出した状態です。出血することで、血液が便に混ざる場合があります。
大腸憩室出血
大腸壁に生じた憩室の血管が破綻して出血します。その際、大量出血する場合もあります。
虚血性腸炎
大腸粘膜の血流が低下することで炎症が発生した状態です。血便が出る場合があります。
血便の検査
最初に問診を行い、血便の状態や色、量などを確認します。これらの情報は、緊急度の把握や検査方法の選択に役立ちます。その後、胃カメラ検査や大腸カメラ検査、レントゲン検査、脈拍・血圧測定などを必要に応じて行います。また、血液検査を実施して炎症や貧血の有無・その程度を把握します。
血便の治療
血便が生じていても病気が原因ではないこともあります。軽い炎症や一過性の出血が原因であれば、自然に改善することもあります。なお、出血原因や部位によっては、血便の慢性化や重大な病気に繋がる恐れもあります。問診・検査によって、血便の原因を突き止め、最適な治療をすることが大切です。また、脱水症状や下痢が起こっている場合は、それらも併せて治療し、二次的なリスクをできるだけ少なくすることが重要です。
当院では大腸カメラ検査を行っており、炎症やポリープ、がんなどの早期発見・早期治療を行えます。血便が出ている場合、一度ご相談ください。
血便の色について
基本的に、血便の色は鮮血便(鮮やかな赤色)や黒色便(黒っぽい色)です。なお、出血部位や量によって差が出ることがあります。鮮血便は、肛門付近や直腸など比較的肛門に近い部位からの出血が原因で、便に新鮮な血液が混ざっている状態を指します。
一方で、黒色便は胃などの上部消化管や小腸などの下部消化管の出血によって起こりやすいです。消化液によって血液が酸化し、黒っぽい便になります。このような血便はメレナといわれる場合もあります。