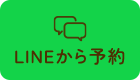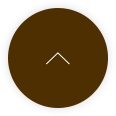バレット食道とは
 食道粘膜を覆う扁平上皮が、胆汁や胃酸などによる慢性的なダメージによって円柱上皮に変性した状態を、バレット食道といいます。この変性した粘膜の長さが3cm以上の場合はLSBE(Long Segment Barrett's Esophagus)、3cm未満の場合はSSBE(Short Segment Barrett's Esophagus)と診断されます。バレット食道の長さが長くなるにつれて、バレット腺がんを発症しやすくなります。
食道粘膜を覆う扁平上皮が、胆汁や胃酸などによる慢性的なダメージによって円柱上皮に変性した状態を、バレット食道といいます。この変性した粘膜の長さが3cm以上の場合はLSBE(Long Segment Barrett's Esophagus)、3cm未満の場合はSSBE(Short Segment Barrett's Esophagus)と診断されます。バレット食道の長さが長くなるにつれて、バレット腺がんを発症しやすくなります。
日本人の場合、バレット食道の多くはSSBEであり、バレット腺がんの発症リスクはそこまで高くありません。
なお、食道がんの中でバレット腺がんの占める比率は7%程度であり、今後注視すべき病気と考えられています。
バレット食道の症状
-
胃もたれ
-
嘔吐
-
胸痛
-
胸焼け
-
嚥下障害
-
食道の違和感(食道に異物感や詰まり感がある
-
腹部膨満感
-
嗄声
-
声のかすれ
など
バレット食道の原因
バレット食道は、逆流性食道炎によって起こる病気です。
胃酸の逆流によって食道粘膜がダメージを受け、粘膜が回復する途中で胃上部の円柱上皮が拡大していき、粘膜が置き換わります。
昨今は、食生活の欧米化などを背景に日本で逆流性食道炎の発症者数が増えており、それと同時にバレット食道の発症者数も増加すると考えられています。
バレット食道の検査
逆流性食道炎の症状が起こっている場合、バレット食道が起きている可能性があります。
バリウム検査によってバレット食道の確定診断をすることは不可能ですので、胃カメラ検査が不可欠です。胃カメラ検査では、食道胃接合部付近の粘膜を詳細に確認します。構造や色調の差異から円柱上皮と通常の食道粘膜を区別し、バレット食道の確定診断を下します。
また、胃カメラ検査では組織採取も行うことができ、採取した組織を顕微鏡で調べることで、形態のいびつさや細胞の増殖度について確認できます。
バレット食道の治療
バレット食道自体を解消する治療法は現時点で確立されておらず、逆流による症状を改善させるための治療を行います。
逆流性食道炎を放っておくとバレット食道が悪化しやすくなるため、逆流性食道炎の方は治療を実施しながら、年に一度は胃カメラ検査を受けて経過を観察しましょう。
バレット食道と
バレット食道がんについて
バレット食道の患者様の中には、病状が悪化して、バレット食道がんを発症する可能性がある方もいます。バレット食道からバレット食道がんに進行するまでの時間には個人差がありますが、バレット食道がんの悪化スピードは早く、深刻な状態に陥る恐れがあります。
バレット食道がんの発症を防ぐためには、バレット食道の早期発見・早期治療が欠かせません。そのためには胃カメラ検査を定期的に受けて、バレット食道の原因となる逆流性食道炎などを発見し、早期に治療できるよう努めましょう。
バレット食道のよくあるご質問
バレット食道と診断された場合、食事の注意事項はありますか?
食道に胃酸が逆流して食道粘膜に炎症が発生することで、バレット食道が起こります。
食道への逆流を抑えることが必要で、香辛料などの刺激物の摂取を避ける、高脂質な食事を控える、暴飲暴食をしないといった食事内容の見直し、食後すぐに寝ない、早食いしないなど食事習慣の見直しも重要です。
バレット食道と診断されましたが、食道がんの発症リスクがありますか?
日本人のバレット食道は、ほとんどがSSBEというバレット粘膜が3cm未満の状態です。
この状態は食道がんに進行するリスクはそこまで高くないといわれています。
なお、LSBEというバレット粘膜が3cm以上の状態は、食道がんの発症リスクが年間約1.2%といわれており若干高くなります。
SSBEと診断されましたが、治療を受けなければなりませんか?
現在のところ、バレット食道自体の治療法は確立されていません。
なお、逆流性食道炎を放っておくと、バレット食道がより悪化する場合もあるため、逆流性食道炎の治療と併せて、食生活などの生活習慣の見直しが重要です。