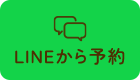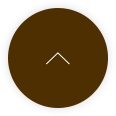アニサキス症とは
アニサキスは魚介類に棲みつく寄生虫です。
魚介類を十分に加熱していない状態、もしくは生で食べてから、強い胃の痛みが起こった場合、アニサキス症の恐れがあります。
アニサキスの体長は2~3㎝であり、糸くずに似た半透明の形状で、目視で確認することもできます。
アニサキス症の症状
-
腹部の張り
-
激しい腹痛
-
強い吐き気
-
激しい嘔吐
-
みぞおちの強い痛み
など
アニサキスが体内に寄生していると、上記のような症状が現れます。
アニサキスは数日から1週間程度で死滅して症状は解消しますが、死滅するまでの間は強烈な症状が長引きます。
アニサキスは胃カメラ検査によって取り除くことができます。アニサキスを放っておくと、腹膜炎などの重篤な状態に進行するケースも稀にあるため、なるべく早めに当院までご相談ください。
アニサキス症の原因
魚介類を十分に加熱していない状態、もしくは生で摂取すると、生きた状態のアニサキスが体内に侵入し、胃粘膜に寄生します。
特に、サンマやサケ、イカ、サバなどの魚介類によく寄生しているといわれています。
最終宿主はイルカやクジラなどの哺乳類ですが、人間が宿主になることはないため、アニサキスが体内に入っても数日から1週間くらいで死滅します。
なお、死滅するまでは強い痛みなどの辛い症状が続きます。
アニサキス症の種類
アニサキス症は、次のようなタイプに分けられます。
胃アニサキス症
アニサキス症の多くが胃アニサキス症に当てはまります。
アニサキスが寄生した魚介類を食べてから数時間経過後に、強い痛みなどが生じます。
また、蕁麻疹や発熱などのアレルギー症状が現れる場合もあります。
腸アニサキス症
腹痛、吐き気・嘔吐などの症状が起こります。
腸アニサキス症では、アニサキスが寄生した魚介類を摂取してから、半日~数日経った後に症状が現れる場合もあるため、アニサキスによる症状だと自覚できない場合があります。
なお、腸閉塞や腸穿孔による腹膜炎など深刻な状態に陥ることも稀にあるため、注意が必要です。
消化管外アニサキス症
非常に珍しいケースですが、体内に入ったアニサキスが消化管を貫通して、別の場所に移ることがあります。
移った場所によって最適な治療は異なります。
アニサキスアレルギー
アニサキスに対してアレルギーをお持ちの方は、生きたままのアニサキスのみならず、アニサキスを除去した魚介類や死滅したアニサキスを摂取してもアレルギー症状を起こす場合があります。
この場合、十分に魚介類を加熱しても症状が起こる恐れがあるため、アニサキスが寄生する可能性がある魚介類を食べないことが重要です。
アニサキス症の検査
胃アニサキス症
アニサキス症の多くは胃アニサキス症です。胃カメラ検査で胃粘膜をリアルタイムで観察することで、アニサキスが寄生しているかどうかを確認できます。アニサキスが見つかった場合、検査中に取り除くこともでき、痛みなどの症状はすぐに改善します。
なお、胃が空っぽの状態でないとアニサキスを全て取り除くことは不可能です。そのため、アニサキス症の恐れがあれば、食後7時間経って胃が空っぽの状態で胃カメラ検査を受けるようにしましょう。
なお、最後の食事からそこまで時間が経過していない方には、超音波検査を実施する場合があります。
腸アニサキス症
腸アニサキス症の恐れがあれば、腹部超音波検査もしくは大腸カメラ検査で確認します。その他、血液検査で抗アニサキス体を調べる場合もあります。なお、腸アニサキス症が起こるのは非常に珍しく、1%程度の確率といわれています。
アニサキス症の治療
腸アニサキス症
症状に合わせた薬を使用し、症状を軽減させます。
消化管外アニサキス症
アニサキスが寄生している部位を突き止めるために、精密検査を行います。寄生部位に合わせた治療を実施しますが、発症すること自体が非常に珍しいです。
アニサキスアレルギー
抗アレルギー薬・抗ヒスタミン薬を使って、蕁麻疹などのアレルギー症状を軽減させます。重度のアレルギー症状があれば、ステロイド剤を使います。
アニサキス症の予防
魚介類の加熱が不十分な状態、あるいは生で食べるとアニサキス症を発症する恐れがあります。
アニサキスは、60℃以上で1分間加熱する、もしくは70℃以上で加熱することで死滅します。
また、-20℃以下で24時間冷凍することによっても死滅します。したがって、一度冷凍してから解凍した刺身であれば、アニサキス症の心配はありません。また、アニサキスは内臓にいる可能性が高いため、魚介類の内臓の生食は控えてください。
なお、アニサキスアレルギーの方は、死滅したアニサキスでもアレルギー症状を生じる場合があります。また、アニサキスを全て取り除いた魚介類でもアレルギー症状が生じる場合があるため、加熱しているかどうかは関係なく、アニサキスが寄生する可能性のある魚介類を食べないことが大切です。