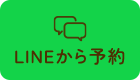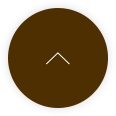肛門内科とは
 肛門内科は、肛門痛、肛門周囲皮膚炎、痔、肛門ポリープ、直腸脱など肛門付近に起こる症状・病気を対象とした診療科です。
肛門内科は、肛門痛、肛門周囲皮膚炎、痔、肛門ポリープ、直腸脱など肛門付近に起こる症状・病気を対象とした診療科です。
特に、痔は相談されることが多い病気ですが、切れ痔、いぼ痔、痔ろうなどの種類があり、血便や下血などの症状を伴うことが多いです。
なお、血便や下血が出たとしても「痔が原因だろう」とご自身で判断しないようにしましょう。血便の原因には痔の他にも、クローン病や潰瘍性大腸炎などの炎症性腸疾患や大腸がんなども考えられます。血便や下血などの症状が現れた方は、一度当院までご相談ください。
肛門の病気
いぼ痔(痔核)
いぼ痔とは、強くいきむことで肛門に負荷がかかり、肛門周囲の血管(静脈叢)がうっ血して腫れた状態です。静脈叢は、肛門の周りに存在する毛細血管の集まりで、クッションのような役割を果たしています。
いぼ痔は2種類に分けられ、肛門と直腸の繋ぎ目である歯状線を境に、直腸側に発生したいぼ痔は内痔核と呼ばれ、肛門側に発生したいぼ痔は外痔核と呼ばれます。
内痔核
歯状線の内側の直腸粘膜に発生したいぼ痔です。妊娠・出産、便秘などによって強くいきむことが原因です。粘膜には知覚神経が通っていないため、痛みは生じません。そのため、排便時の出血や痔核の脱出によって自覚するケースが多いです。飛び出した痔核は、最初の内は自然に内側に戻りますが、徐々に指で押し込まないと戻せなくなり、最後は押し込んでも戻せなくなります。
外痔核
歯状線の外側に発生したいぼ痔です。皮膚部分には知覚神経が通っているため、激しい痛みを生じます。なお、出血は起こりません。肛門に大きな負荷がかかる症状、行為が原因となり、例えば下痢や便秘、香辛料など刺激物の摂取、アルコールの過剰摂取、立ち仕事、デスクワーク、長時間の運転などが挙げられます。
切れ痔(裂孔)
切れ痔とは、太い便や便秘などによる硬い便が通過することで肛門の皮膚が切れたり、裂けたりした状態です。
便秘が原因で強くいきむと切れ痔が悪化し、その痛みを避けるために便意を我慢すると、さらに便秘が悪化する悪循環に陥ることがあります。
また、下痢による勢いの強い便の通過により切れ痔が起こる場合もあります。切れ痔ができると、排便時に激しい痛みが起こりやすく、ペーパーで拭いた際に血が付く場合もあります。
また、切れ痔が慢性化すると、徐々に傷が大きくなって潰瘍やポリープに繋がる場合があります。また、患部が瘢痕化(はんこんか)して肛門が狭窄し、排便に支障をきたすようになります。
切れ痔の根本的な治療と再発防止のためには、原因となる便秘・下痢をきちんと治療することがとても大切です。
当院では、消化器病専門医が便秘治療を担当しますので、一度ご相談ください。
痔ろう(あな痔)
肛門と直腸の境目にある歯状線には肛門陰窩と呼ばれる小さな窪みが並んでいます。この肛門陰窩に便が侵入し、細菌感染によって炎症・化膿が起こった状態が肛門周囲膿瘍です。腫れや痛み、熱感などの症状をきたし、肛門のかゆみや下着の汚れなどの症状も起こります。
肛門周囲膿瘍が悪化すると、膿が皮膚の下でトンネルのような通りを作り、最終的には皮膚に穴が開くことがあります。この通り道のことを「瘻管(ろうかん)」といい、これを通じて膿が排出され、トンネルが残った状態が痔ろうです。トンネルは自然に穴が消えることはなく、痔ろうの治療には手術が不可欠です。放っておくとトンネルの構造が複雑になって、治療が難しい状態となる恐れがあります。クローン病によって痔ろうをきたす場合もあります。
なお、手術が必要な場合は、連携している高度医療機関を紹介いたします。
カンジダ感染について
肛門でカンジダ感染が起こった場合は抗菌剤を使用します。肛門痛については痛みが起こる回数や時間によって適切な処置が異なります。
注意すべき肛門の病気
肛門の出血や痛みがある場合、炎症性腸疾患(クローン病、潰瘍性大腸炎)、アメーバ腸炎、出血性ポリープ、大腸がん、肛門がんなどが潜んでいる可能性があるため、注意が必要です。そのため、出血や痛みの症状があれば、「痔が原因だろう」と自己判断せず、一度当院までご相談ください。
肛門の病気の診察の流れ
1問診と診療の準備
個室で問診を実施し、症状の内容、いつから始まったのか、特にお困りの内容などを確認します。
問診後は診察ベッドに寝ていただき、タオルをかけて診察の準備を行います。服を脱いでいただくことはありませんが、お尻を確認できるところまで下着を下げていただきます。
緊張すると筋肉が収縮して肛門が閉じてしまいます。負担の少ない検査となるように、クリニック側でも配慮しておりますので、できるだけ脱力して落ち着いた状態で検査を受けていただけますと幸いです。
2診察
診察では最初に指診を実施します。医療用手袋をはめて指に麻酔ゼリーを付けた状態で、肛門に指を挿入し、しこりやポリープができていないかをチェックします。指診が終わった後、肛門鏡検査を行い、肛門内部の病変の有無を確認します。
肛門内視鏡にも麻酔ゼリーをたっぷり塗っているため、痛みは起こりません。また、どちらの検査も無理やり行うことはないので、ご安心ください。
検査後は患部に付着した麻酔ゼリーを丁寧に拭いて完了です。
3処置
診察結果をもとに、軟膏塗布など最適な処置を実施します。
4身支度
検査後は、身支度を整えてお待ちいただけますと幸いです。
5ご説明
検査結果を丁寧にお伝えします。今後の治療方針は、患者様とご相談しながら決めていきます。